35年の実績で、皆様と共に歩んでゆきます。
| 当サイトと連動し、平日毎日複数本のブログ発信をし、経営コンサルタント歴35年の独断と偏見から何かを感じ取っていただけると幸いです。 経営者・管理職向けの記事、それを裏返すと経営コンサルタントなど士業の先生方にも参考となります。 |
| Yahooブログ アメブロ ブログ人 ドリームゲート |
|
||||
■ ご飯と飯はどう違う 01
「ご飯」という言い方は、誰でも使いますが、関白亭主が帰宅するや「メシ~ッ」と大声を出すという風景は近年はほとんど見かけなくなりました。
ところで、「ご飯(はん)」と「飯(めし)」との違いは何でしょう。「メシ」というと上述の例が浮かびますし、品のない言い方のように聞こえます。しかし、この両者には誰にでもわかる違いがあるのです。
まず、想像がつくのは「ご飯は温かく、メシは冷たい」ということです。しかし、これは正解とはいえません。炊きたての銀しゃりのことを「ご飯」といい、それ以外は全て「メシ」です。すなわち、たきたてのごはんが冷めるとメシに降格になります。
「五目ご飯」という具が混じった食べ物がありますが、これは「五目飯」というのが正しい言い方です。銀しゃりだけが「ご飯」ですから、混ざりモノ、たとえそれが高価な松茸であってもご飯ではなく、メシとなります。
すなわち、江戸時代には、ご飯というのは、今日の赤飯とか、松茸ご飯問い言った食べ物のように贅沢品といえます。
 江戸っ子は、その銀しゃりを毎日食べていました。地方の庶民は玄米を食べるのが普通な時代ですので、江戸庶民は贅沢をしていたといえます。玄米をつくことにより、「二分搗き」とか「五分搗き」というように玄米にランクがあります。最終的には白米になります。
白米、すなわち銀しゃりを毎日食べていたので、江戸っ子には脚気が多かったと言われています。そのために脚気のことを「江戸患い」といいました。
ただし、三色銀しゃりを食べていたわけではなく、朝ご飯を炊いて、昼はメシ、夕食にはお茶漬けを食べていました。一日三食というのは江戸中期以降のことで、それまでは二食で足らしていました。江戸中期以降も二食ですごしている家庭もあり、一日何度食べるかは、その家の風習といえそうです。すなわち、一日に5~6回も食事をする家もあれば、一日一回だけのどか食いの家もあります。
三食のうち、昼飯が最も豪華で、すなわち昼飯は英語で言うとLunch ではなく Dinnerというべきです。ご存知のように夕食とはdinnerとsupper とふたつの単語がありますが、前者は「晩餐」と訳されることが多いように、一日のうちで最も豪華な食事のことです。すなわち江戸っ子の晩餐は昼なのです。
では、江戸っ子の晩餐(昼食)は、どのようなモノだったのでしょうか。晩餐といわれるゆえんは、昼食には焼き魚が付くので、たとえ冷めた飯ではありますが、時間をたっぷりかけて食事をします。
宮沢賢治の「雨ニモマケズ」では、「一日に玄米四合と味噌と醤油と少しの野菜を食べ・・・」とありますが、江戸っ子は、どのくらいお米を食べていたのでしょうか?
江戸っ子は、一日にお米を五合食べるのが一般的でした。これは、一日二食であろうが三食であろうが、一日のお米消費量は一定でした。すなわち一日二食の家庭では、一回に二合半を食べていたことになります。
そのために、どの家庭にも二合半の升があり、一人前のお米を食べられない人のことを「この一合野郎」と言って罵ったそうです。すなわち、半人前以下と言うことです。
因みに、旧日本陸軍では、一日三食、麦飯2合と定められていた。それだけの米飯を食べないと肉体労働に必要なエネルギーを確保できなかったのでしょう。それからすると賢治の食事は質素であったと言えます。
■ 江戸のご飯は赤茶色 04
江戸下町の風景というと長屋住まいで、井戸端で女将さん達が選択をしたり、お米をといだりしていることを連想する人が多いでしょう。
実は、江戸には「水道」がありました。しかし地中の鉄分を含んだ水が多く、赤茶色をしていました。水源では色は付いていないのですが、水道管が木樋であったために地中の鉄分が滲み込んでしまうのです。
当然その水でお米をといだり、炊いたりするのでご飯に色が付いてしまい、銀しゃりならぬ銅しゃりだったのかもしれません。
もちろん、濾過をしたり煮沸したりしたのです。太い竹筒の節をくりぬき、そこに木炭や小さな砂利と石灰を入れ、そこに水を通して、濁り水のような水を色は完全には消せないものの透けて見えるようにはなっていました。
今日なら、さしずめコンビニやスーパーでペットボトルの水を買うのでしょう。実は、江戸っ子もペットボトルならぬ瓶買いをしていました。われわれがペットボトルの水を購入するようになったのはここ20年にも充たないですが、江戸っ子は、瓶詰め水を配達してもらっていたのです。
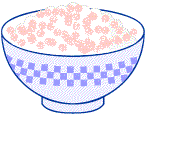 今日、ご飯を釜で炊く家は少なくなりました。ごはんも七輪で炊いていたようですが、一つの長屋で七輪を持っているところは2~3割でしかなかったようです。持っていない家はどうするかというと、持っている家から借りたのです。七輪の使い回しと言うことで、時差出勤ならぬ時差食事で融通し合っていたのですね。今日のように[隣は何をする人ぞ]というような冷たいコミュニティとは大きく異なります。
もっとも、江戸時代はご飯を炊くには朝だけだったので、毎食使い回しをしていたわけではないようです。
因みに昼はほうじ茶で冷や飯で過ごしていました。夜はお茶漬けですから、たくあんでもかじっていたのでしょうか。すなわち昼も夜も「ごはん」を食べずに「めし」を食べていたのです。(当ブログ「ご飯と飯」を参照)
もっとも、江戸時代、江戸以外では、家で煮炊きをするほうが一般的だったようです。
江戸には、独身男性が多く、彼らは屋台で済ませてしまうことが多かったようです。中には三食とも屋台で立ち食いで済ませている人もいました。
屋台というと、鮨や天ぷら、それにそばと鰻が定番でした。彼らが好んで食べるものは、懐具合もあるのでしょうが、そば、鰻、鮨、天ぷらの順で、この四つは「江戸前の四天王」と呼ばれていました。
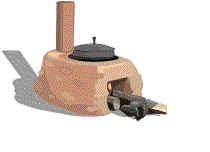 ■ 深川飯とぶっかけ飯 06
東京以外の人には、深川という地名はあまり馴染みがないかも知れません。深川というのは、東京の東、江東区深川といい、「江戸の下町」の風情を残す地の一つといえます。
最近、深川というと、あさりの汁をぶっかけた「深川飯(ふかがわめし)」で有名です。深川めしというのは漁師のまかない食で、すなわち労働者の食べ物だったのです。もっとも「深川飯」というのは近年売り出しのためにつけられた名称で、それまでは「あさり飯」と言っていました。
ただし、あさり飯を女の子は食べてはいけないと言われていました。あさり飯のような「ぶっかけ飯」を食べると、嫁入りの日に雨がふるって言われていたのです。そもそもが労働者の食べ物ですから、女の子が食べる機会は少なかったようです。どうしてもあさり飯のような「めし」を食べたいときには炊き込みご飯にしたそうです。
【Wikipedia】
深川めし(ふかがわ - )は、アサリのむき身を味噌汁の具にしたものを、茶碗や丼にのせた米飯にかけたものである。 気の短い江戸っ子の漁師が飯と汁物を一緒に食べる為に考案された。あさりの産地ではポピュラーなものだが、東京の深川が代表格であり、「深川めし」と呼ばれている。なお、近年増え始めた深川めし屋は炊き込みタイプの上品なものとなっている。
アサリは、他の具(長葱・油揚げなど)とともに醤油などで味付けをして煮る。その後、煮汁でご飯を炊き、炊き上がったら具を戻してかきまぜてできあがり。炊き込みご飯ではあるが、アサリそのものをご飯と一緒に炊き込むわけではない。
因みに、深川という地は富岡八幡宮のある門前町として三代将軍徳川家光の時代から発展してきました。明暦の大火の後に水運を利用して木場がおかれ、問屋街としても発展してきました。
そもそも江戸でも東のはずれの湿地帯であったゼロメートル地帯である江東地区を開拓していた深川八郎右衛門の姓に由来するといわれる。
3代将軍徳川家光の時代から富岡八幡宮の門前町として発達し、明暦の大火ののちに木場が置かれて商業開港地域となりました。材木商人といえば紀伊国屋文左衛門が有名ですが、一時ここに館を構えていたようです。
街が栄えると、深川岡場所も設置され花街となりました。1800年に入る文化年間には岡場所が7カ町もでき江戸の辰巳の方角にあることから、深川の芸者は「辰巳芸者」と呼ばれ、「羽織芸者」がたくさんいる「粋と張りと意気地」の花街となりました。
「張り」というのは、「張り詰める」などという言葉にあるように緊張とか緊迫感ある状況を言います。努力すると結果に繋がる街でもあったようです。
深川江戸資料館 ←クリック
■ 江戸っ子の「御御御汁」??? 08
江戸では、汁物はご飯の時にしか付きません。ご飯は、炊きたての銀しゃりのことで、朝食にしか食べません。すなわち汁物は、朝だけで昼夜に付かないのです。最も昼はほうじ茶で冷や飯を食べ、夜はお茶漬けですので知るものはなくても済んだのです。
「汁物」、すなわち「お味噌汁」ですが、江戸では「おみおつけ」と言いました。もともとは「つけ」すなわち「汁」と言っていたのです。それを丁寧に表現しようと「御汁(おつけ)」と言うようになりました。その「御汁」をさらに丁寧に表現しようと「御汁」に「御」をつけます。御汁に御をつけるので、これを「みおつ汁」すなわち「御御汁」というようになりました。これでもかという江戸っ子気質で、「御御汁」に「お」を重ねて「御御御汁」すなわち「おみおつけ」となったのです。
では、なぜ江戸っ子は、このように丁寧な表現にしたのでしょうか。ひとつには、江戸っ子の負けず嫌いが言葉にも出て来たといえます。ご飯だけではやはり不充分で、一日の活力を御御御汁に求めたので、具は二種類以上を入れました。
具だくさんな御御御汁ですので、どちらかというとけんちん汁のような汁物だったのです。どんぶりというか大きなお椀で御御御汁を食べたのです。
江戸では、すまし汁はあまり食べなかったようです。すまし汁は、明治以降の汁物のようです。
■ 江戸っ子はインスタント好き 09
別項で江戸の御御御汁についてご紹介しました。では、江戸っ子の「だし」はどのようなものだったのでしょうか。
聞いて驚くなかれ、江戸っ子は「インスタント味噌汁」を食べていたのです。前回書いたように、具は二種類以上を用意したのですが、ネギとだし数種類が味噌に練り込んであるものを使いました。今日では、フィルム袋に入ったインスタント味噌汁がありますが、江戸時代には、一色ずつ玉になっているものを総菜屋から購入して使っていたのです。なんと、江戸っ子は合理的なのでしょう。
江戸ではまな板や包丁があまり普及していませんでした。包丁の代わりにブリキ板のような「かなべら」というものを使いました。まな板がないので乱切りで野菜を切ったりしました。屋敷奉公の時に、豆腐のさいの目切りという実技テストがあったそうです。
豆腐は、豆腐屋で買うときにさいの目に切ってもらうこともありましたが、手のひらでぐちゃぐちゃにして御御御汁の中に放り込んだのです。
豆腐の料理法は多彩でした。庶民に最も人気があったのは湯豆腐と田楽です。
因みに、「江戸三白」というと豆腐、白米と大根でした。
江戸時代は、今日より合理的な発想をしていた面もあるようです。
前回、包丁やまな板はあまり使われていなかったということをご紹介しました。では、大根なの根菜類をどのようにしていたのでしょうか?
包丁やまな板を使わないと言うよりは、持たないというか、それ以外にお金を使うことを考えていたのかもしれません。すなわち包丁を持つ代わりに、ブリキ板のような「かなべら」を使って乱切りをしていました。
もちろん包丁を使わないので千六本やさいの目切りなどはあまりしません。一方でお屋敷に奉公するときの実技テストに、それがテストされることがあったようです。
それでは、その他のいろいろなおかずはどうしていたのでしょうか?
上述のように合理的な発想をしていましたから、自前で作るのが大変なものは惣菜屋へ行って購入してきたのです。すなわち、今日、スーパーやコンビニの総菜コーナーを利用する感覚で、惣菜屋を利用していたわけです。
惣菜屋も心得たもので、一人用、二人用というようにパッケージ化して販売しているから、人数に応じた組み合わせをすればムダな買い物をしなくても済むようになっていました。
値段も手頃で単身者にも便利でした。
■ 四文屋 11
オリジンという総菜チェーン店をご存知の方も多いと思います。100グラム○円で、いろいろなおかずを買うことができます。
江戸時代の「四文屋(しもんや)」は、さしずめ今日のオリジンのようなお店です。煮売り屋とも呼ばれていたようで、何でも四文で買えます。芋の煮っころがしから大根の煮つけ、麩を煮たものまで何でもあったようです。
江戸っ子のたんぱく源は豆腐でした。豆腐は切り売りされているので、江戸っ子は、豆腐が崩れないような容器を持って買いにいくのです。私が子供の頃も豆腐屋さんに鍋を持って買いに行った記憶があります。
「一里腐屋」という「振り売り」が街の中を売り歩きます。売り声を出して売り歩くのですが、豆腐屋さん独特の笛は時代がもっと下ってからのようです。一豆腐屋さんの声が聞こえると「一丁おくれ」というふうに買っていました。
合理性は、今日の商売人も顔負けで、月契約制度もありました。「わが家には毎日○刻頃、一丁を届けてくれ」というような約束して、定時に届けてもらう方法です。
江戸時代の男性は、女性を口説くときに「食事でもしませんか?」などと言ったのでしょうか?
江戸の男性は「初物」が好きで、女性を口説くときにもこれを利用したようです。その中でも、よく知られるのが「初鰹」です。
女性を口説くときには、初鰹を使ったそうです。ただし、4月8日以降に鰹を食べさせるのは「野暮」なので、それ以前に、自分で釣った鰹をもてなして、女性を口説くのです。
しかし、旧暦の4月8日ですから、なんとか鰹を釣ることが不可能だったようです。それだけに自分で釣った鰹の価値は高く、女性を口説くには最大の武器と言えます。
江戸っ子の男は、それだけで終わりません。簪(かんざし)や紅をプレゼントするのです。
しかし、現実には、鰹はボテ売りから買ったようで、2~4両もしたと言うから、恋もお金がかかりますね。
■ 江戸の離婚 13
江戸っ子の男は、女性を口説くときに鰹+プレゼントという話をしましたが、プレゼントには簪(かんざし)や紅が多かったことも書きました。しかし、櫛を送るのは注意が必要です。
櫛を贈るということは、プロポーズをすることなので、所帯を持っている人には櫛を送れません。
なぜ、櫛を送るかというのも日本人らしさがあります。「くし」の「く」は「苦労」の「く」です。「し」は「しんどい」の「し」から来ています。所帯を持つのは「苦しくて、しんどいもの」から来ているそうです。
「しんどい」というのは、江戸弁でしょうか?
何となく、こじつけのようのですね。
「三行半」というと離縁状で、男性が女性にたたきつけるものと思っていましたが、江戸時代は、女性が強かったので、かかあが櫛を投げ返して、亭主を追い出すことが多かったようです。
追い出された亭主は、かかあの櫛を質に入れて、その夜の宿泊代にしたそうです。
追い出された亭主の中には、そのかかあから突き返された櫛を別の女性にプレゼントして、そこに転がり込む者もいたそうです。
江戸っ子の男は手料理を作って女性を口説いたようです。自分でそばを打ってそばを振る舞うのがベストな方法でした。
二八そばが多かったようで、そば粉八に対し、つなぎとしての小麦粉が二の割合でした。それを薬味と共に食べたわけですが、江戸っ子は、そばにネギを入れないで、陳皮や大根おろし、七味唐辛子で食べました。
陳皮というのはみかんの皮を干したもので、今日でもネットの袋に入れて陳皮を作っている人がいますね。陳皮は薬味として使うだけではなく、風呂に入れて入浴剤に使ったり、消臭剤として燃したりします。
江戸のそば屋は、今日でいうとパブのような存在だったようです。そば屋では今日のような面ではなく、「そばがき」だったのです。
いきなりそばがきで食べるようになったのではなく、時代を遡ると「そば実雑炊」というのがあって、そばの実のままをゆでます。実がそのままですから殻がついたままで、ゆでると、殻だけがはじけて浮いてきます。それをあくと一緒にすくって捨て、味つけをしました。
時代が少し下ると、「そばがき」が誕生しました。その後、そば粉を練って、つみれのように団子状にして、鍋で煮込むようになりました。そば粉を練ることから発展したのが今日のような麺状のそばです。練った物を板の上で延ばし、短冊状に細く切って食べるようになったのは江戸時代中期です。
そばと言っても、今日のようなそばになるまでは長い道のりを経てきたのですね。
■ そばと技術革新 15
江戸のそばの歴史について前回記述しましたが、今日のようなそばになるまでは長い道のりを経てきたのですね。
その過程で、最も貢献したのが小麦粉で、画期的な技術革新と言えます。つなぎがないとブツブツと切れてしまい、麺状にはなかなかなりにくいのです。「十割そば」というのが今日ありますが、小麦粉の代わりに卵をつなぎに使うという話を聞いたことがあります。
因みに、麺状のそばは「そば切り」と言って、当時主流のそばがきとは区別していました。時代劇で「そばを食べた」と言った場合は、上述の雑炊かそばがきのことで、そうでないと時代考証に引っかかります。
やがて、もりやざるという形で食べるようになります。当時から、「もり」と「ざる」の区別はあったようですが、今日とはちょっと違っていたようです。
「もり」というのは、皿に盛った冷たいそばのことです。せいろに盛ったそばは「せいろ」と言われ、ざるに盛ったのが「ざる」でした。今日のように、海苔がかかっているのは「海苔かけ」と言って区別していました。
海苔は「江戸前」です。浅草寺門前仲見世で売られていたことから「浅草海苔」とも言われています。江戸の前にある海でとれる海苔なので「江戸前」を言われました。因みに江戸前とは大森当たりまでを言ったようで、江戸土産として浅草海苔が定着したのは江戸時代も後期になってからです。
そばの話しに戻りますが、温かい汁そばは、「かけ」と言われましたし、冷たいままやぬるい状態のそばを「ぶっかけ」と言いました。
分量は、やや少なめで、ゆであがり状態で70~80gといいますから、セット物のランチについてくる小鉢よりも少ない量だったのです。だからといって何杯も食べるのは江戸っ子の風上に置けない野暮な行為なのです。「腹が減ったから、そばでも満腹になるまで喰ってみようか」などということは江戸っ子は言わなかったのです。
そば屋というのは、パブでちびちびとやりながら時間を過ごすような場所です。ちょっと時間があるから「そばでも食おうか」という雰囲気だったのです。
■ 江戸流儀による寿司の“喰い方” 16
江戸っ子は、「食べる」という言葉より「喰う」という表現の方がぴったりします。そばと共に江戸というと江戸前寿司です。江戸も中期となると、寿司も今日と同じにぎり寿司です。
海苔巻きも当時からありました。恵方巻に代表される上方の太巻きではなく、細巻きです。江戸っ子は、寿司を飯の代わりと言うより酒の肴としてつまんでいました。今日では海苔巻きなどの巻物は最後に頼むのが常識のようですが、江戸っ子は酒のつまみとするのですから、飲み始めから巻物を頼んでいました。
お酒を飲む人は、刺身をつまみに一杯やってからお鮨を始めるというパターンが多いと思います。実はこれは江戸では関西風とみなされ、江戸っ子は、そんなのは野暮なことと感じていました。
江戸っ子は、上述のようにいきなりお寿司を食べたり、ときには銀しゃり、すなわちご飯(飯ではないことを当ブログで紹介済み)を頬張ったりしました。お酒に対して生魚は主張が強すぎると感じていました。すなわち、その中間的な存在として、生魚の強さを銀しゃりがとりもって、酒の肴としてちょうど良い加減と言えるのです。
巻物も江戸流がありました。江戸時代には鉄火巻きはありませんでした。マグロというのは、寿司飯なしで、海苔で直接巻きます。四角く切ったマグロを巻くので,マグロ巻というのは四角いのです。それに対してキュウリやかんぴょうは丸く巻いたのです。
当ブログでも紹介しましたが、赤身の良いところだけを見繕って醤油とみりんで浸けた「ヅケ」として食べていました。マグロは「下魚」とみなされていました。今日珍重されているトロなどは見向きもされなかったと言いますからもったいない話ですね。私が江戸時代に生活していたら、わずかな食費で生活できたかも知れませんね。
■ にぎり寿司はなぜ二巻ずつ出てくるのか 17
にぎり寿司は、回転寿司だけではなく、お寿司屋さんでカウンターで握ってもらうときも、二巻ずつ出てきます。これは、幕末から始まったことです。
その理由は、江戸っ子の骨格にあるそうです。江戸っ子というのは、頭が大きくて、顎のえらが張っていると言われています。日本人は、北方系と南方系とがあり、耳かすがカサカサか、しめっているかの違いがその両者にあると言われています。骨格も違うのかも知れません。
話が少々脱線してしまいましたが、寿司がなぜ二巻一組で出てくるのかというその理由に戻ります。
江戸っ子の骨格は、口の中の容積が大きいため、にぎり寿司の大きさが大きく、押し寿司やなれ寿司が主流であった上方の人には大きすぎたのです。上方の人には一口で食べられないので、真ん中から一つに切って出したことから、二巻ずつ出されるようになったようです。
にぎり寿司というのは、一巻を一口で頬張るのが正しい食べ方で、上品ぶって1つを2口にかみ切って食べるのはマナー違反だそうです。
回転寿司などでは、ネタが小さく、ちょこんと小さなしゃりの上に某氏のように乗っていますが、高級寿司店へ行くとネタの重さにしゃりが潰されて見えないほど大きいですね。あれを一口で食べるには、女性でなくて我々男性でも少々勇気が要ります。江戸時代の上方の人は、そんな気持ちで江戸前の握りを食べたのかも知れませんね。
■ 江戸の料理屋 18
東京の下町の一つとして当ブログで深川を紹介したことがあります。そこの鎮守社が富岡八幡宮で、深川八幡とも呼ばれています。ここのお祭りは江戸三大祭りの一つです。その賑やかさの象徴とも言われるのが、見物客でごった返した永代橋の崩落です。文化四年(1807)のことでした。
その様に人の集まるところですが、周辺に料理屋さんがありません。
深川だからないのではなく、深川芸者が活躍したところですから、料理屋がないわけではないのです。江戸全体に料理屋が少なかったのです。少ないから予約制でした。だから、フラリと寄ってそこで料理を食べるなどと言うことはできませんでした。
料理屋さんは、一月くらい前に予約をして利用するのが一般的でした。ホスト役である宴を催す主人が、額を寄せ合って、当日の献立をつめていくのです。どのような料理を出すかだけではなく、料理長を誰にするのか、包丁とり、煮方などの担当、料理の仕方や出す順番や演出方法などを事細かに決めた上で当日を迎えるのです。
料理屋を利用するのは、本当の金持ちしか利用しなかったのです。少なくても中流以上でないと利用できなかったのです。
では、江戸っ子が好きそうなどんちゃん騒ぎはしなかったのでしょうか?
もちろん、江戸っ子のお金持ちはどんちゃん騒ぎが大好きでした。それを料理屋でやる風習がなかったのです。
■ 江戸の居酒屋 19
江戸の居酒屋というのは、現代の居酒屋を連想するのとは少々違っていました。
つまみは味噌とか目刺しくらいしかなかったのです。それをつまみながら升酒をキュッと引っかけることができる場所でしかなかったのです。現代の立ち飲み屋を想像すると近いかも知れません。
もちろんメニューはありません。時代劇でメニューのような物が壁面に貼ってあったりしますが、あれは時代考証がきちんとできていないのです。
メニューがないし、その日によって出せる物が異なることがあるので、客は「できますものは?」と訊くのです。
テーブル席もありませんでした。畳の上に銘々膳やお盆をおくスタイルです。
では、飲み屋で何かを食べたいときにはどうするのでしょうか。
持込です。近所の屋台に頼んで、自分が行く飲み屋を指定して持ってきてもらいます。現代の雀荘のスタイルです。
■ 江戸女性とお酒 20
三行半は女性がたたきつけるモノであることを当ブログでも紹介したとおり、江戸の女性は強かったのです。
花見などと言うと大ぴらに飲めたのです。家でも結構飲む女性が多く、いわゆる「キッチン・ドリンカー」はすでにこの頃から始まっていたのです。
主人が仕事で外出するのを送り出すと、魚屋を呼んではサクで生魚を買い、若い魚屋を相手に、茶碗酒を楽しんだりしたのです。
江戸では「ばれない嘘は嘘じゃない」と言われていて、自分達の行為を正当化していたようです。
江戸時代は、地酒だけでは足りず、上方から「下り酒」が大量に入っていました。どぶろくや焼酎の密造も相当行われていました。江戸の人口の四割が飲酒人口として、正規のお酒だけを対象として計算しても、平均すると一人一日二合半弱を飲んでいたことになります。
フランス人は、ワインを水代わりに飲むと言われています。実は、江戸も水が悪いため、飲料水を買っていたということを当ブログでも紹介しました。
江戸の飲料水の代金は、お酒と余り変わらないこともあり、お酒が好まれて飲まれました。
「江戸の酒は酒くさい水だ」と言われるほど薄かったといいます。江戸で市販されているアルコールの度数は、現代に比べると低かったのです。
酒を造る技術が低かったのではなく、酒屋が希釈して販売していたのです。ただし、上述の計算は、原酒の量に基づいていますので、江戸の人達の酒好きは相当だったと言えます。
因みに「下り酒」というのは、上方から樽廻船によって運ばれてきました。「下り酒」を専門に扱っている問屋は、初期には日本橋や京橋周辺にありました。今日お酒問屋で有名なM屋の本店は京橋にあります。
酒問屋街は、江戸後期に入ると霊岸島にある新川地区に移転しました。「新川の酒問屋」と言われるほどにまでなりました。
霊岸島は、中央区にあり、現代では島ではなく、埋め立てられてビジネス街になっています。東京駅から真っすが行くといまだに霊岸橋があり、そこから先が霊岸島であることがわかります。
江戸時代の酒の”通”は「原酒」を飲んでいました。モルトウィスキーならぬ、モルト日本酒を嗜んだのです。 小売店が希釈する前の原酒を樽からジューッと音を立てて升についでもらうのです。 江戸っ子は、辛口の酒が好きなように誤解されがちですが、江戸の酒は、甘口でした。それも相当な甘口だったようです。 甘口であると言うことは、手をかけてある酒と解釈され、「甘口」を「うまくち」と読ませていました。 上方から樽廻船で送られてきた下り酒の代表は「灘」で、珍重されていました。ご存知のように灘の酒は辛口です。 樽に詰められた灘の酒は、船をゆりかごにして揺られているうちに良い具合に熟成されたのです。江戸に着くまで約20日、これがちょうど熟成期間として最適だったのです。 樽材である吉野杉の揮発性香油が溶け出して、マイルドな甘口になるのだそうです。灘の酒は、地元で飲むより江戸で飲んだ方がうまいと言われています。 その酒が、裁量の酒とされているので、江戸っ子は甘口を好んだわけです。 江戸時代に「武蔵野」という大きな杯がありました。ススキを前景にした満月が描かれていました。この杯は一升以上もの酒が入るのです。満月にススキという図柄から「野見尽くせぬ」・・・・・「飲み尽くせぬ」というしゃれが込められているのです。 相撲取りが優勝したときに飲む大杯を連想して、その大きさをイメージしてください。 この大杯を使って、八升五合もの酒を飲んだという記録があります。ただし、真偽の程はわかりません。 日本酒だけではなく、焼酎もあり、実は「アラキ」今日では「アラック」と呼ばれているウォツカもありました。ロシアから北前船が運んできたのです。 北前船が運んだ昆布ですが、これはロシアでは海に生える雑草ですので、日本漁船が昆布を採るとそのお礼のようにしてウォツカが提供されてようです。当時は鎖国政策が採られていたので、ビジネスとしての代金は取れませんが、ウォツカが対価の一種であったといえます。すなわち、鎖国下での貿易が行われていたのです。 この酒のみ大会には、武士も町人も、誰もが参加できます。スポンサーが付いた催しものなので参加費などとみみっちいことは言わず、飲み放題です。当然スポンサーはその話題作りのためにお金を出すのですから、結果が発表されるときにはスポンサーの屋号が入ります。 ちなみに「北前船」は当ブログでも紹介したことがありますが、江戸時代の中期以降、明治時代初期にかけて日本海を廻ってのビジネスです。船主は、船を持った移動販売船といったところで、商品の仕入や船の運航など、全てのリスクを負っていました。すなわち、運輸業ではないということになるのです。 商品は主に北海道や北東北から調達し、途中寄港しながら、下関を回って「大坂」(今日の「大阪」)まで運んで売りさばきました。 帰りは、空船で変えるのではなく塩や酒など関西地方の物資を運んでビジネスをしたのです。 ■
■■ 江戸の良い亭主の条件 23 江戸時代の長屋では朝ご飯は亭主が準備をしました。ご飯が炊けると「おっかあ、飯が炊けたぞ」と奥さんを起こすのです。ご飯、すなわち炊きたての銀しゃりに買ってきたお総菜を付けて食べたのです。 今日、モーニング・コーヒーをご主人が立てるお宅がありますが、最先端を行っているのではなく、江戸時代の二番煎じなのです。 当ブログでも紹介しましたが、亭主が仕事に出かけると刺身で一杯やるのがおっかあの一日の始まりです。 では、何故江戸の男はそこまでやるのでしょうか。 答えは・・・・・ 江戸時代は、女性が強かったということは、三行半は男からではなく女性からたたきつけるものだと言うことを紹介したとおりです。すなわち、女性に尽くさないと、女性の方がサッサと家を飛び出して、男は捨てられてしまうのです。 おっかあに、他の男へ乗り換えられないように、江戸っ子はおっかあに尽くしたのです。すなわち、江戸の亭主の条件は、ご飯が上手に炊けることなのです。 それだけではありません。おっかあを丁寧にマッサージするのも亭主の役目ですし、子育ても上手でないといけません。 江戸は、女性にとっては天国だったのかも知れませんが、江戸のおっかあは、長屋から出ることはほとんどなかったようです。 あなたは、どちらが良いですか? 「江戸時代は女性が強かった」とこのブログでも紹介しました。江戸というのは女性の人数が多いのですが、男性を相手にする仕事をする人などが多かったようです。したがって、結婚する女性の数は少ないので、江戸っ子の男にとっては激しい競争と、婚活活動が求められたのです。 戯曲家の北方謙三氏は「もし僕が江戸で生活していたとしたら戯作者だから、まず朝ご飯つくってくれる人を一雇って・・・・・」と言っています。 実は、あまり派手な暮らしをすると、お縄になってしまうそうです。 「縄」なら良いですが、「手鎖」をされて刑を受けなければならないのですから、「人権」などと言っても認められない時代ですね。 「戯作者」というのは、町人の世相や風俗を題材として扱った洒落本・滑稽本です。人情本・読本・草双紙などを著した人たちのことで、著名人として十返舎一九、山東京伝、式亭三馬、滝沢馬琴、柳亭種彦などの名前はお聞きになったことが多いでしょう。(脚注より) ■■ 江戸のおしゃれ 25 江戸時代に庶民が着ている物は、江戸と上方はもちろんのこと、時代的に前期と後期でも大きく異なります。江戸の人が上方に旅をすると、例え着ている物を急いで着替えても、上方ですぐに「関東者」ということがバレバレです。 江戸では、享保年間(1716~1736)を境に変化をしました。それまではもっぱら上方の真似でしたが、享保以降は、着こなしも髪型も大きく変化をしました。化粧法もまたしかりです。 上方では着る物はきっちりと着つけをしましたが、江戸では、はだらしく着て前がはだけてしまいました。着物の仕立ても、打ち合わせが浅いことも一因です。女も懐手をすることが多く、胸もはだけてしまいます。 柄の好みも江戸と上方では異なりました。上方の女性はきれいな色が好きでした。それに比べて江戸の女性は、どちらかというと渋めの柄を好んだ用です。 「赤ぬける」という言葉があり、「赤なしで勝負する」という意味から江戸っ子は、「赤は身につけないぞ」と粋がり、「赤い色などを身につけなくても、色気が出るようにする」のが、江戸の風習です。 「垢ぬける」というのはここからきているようです。ただし「垢抜ける」という言葉は、もともとは「体を磨き込んで垢のない体にする」という意味です。 もちろん、女性にとっては、最後は赤が「決め色」です。「今日こそは・・・」という、ここ一番では赤い紅をさしたり、赤い下着をつけたりして挑みます。すなわち勝負のときのために、「赤」はとっておく、奥の手なのです。 赤は江戸時代の女性の決め色ですが、男性の決め色は紫です。紫の襟をチラッと出すのが、粋な男の身だしなみです。 着物姿の女性の赤い蹴出し(腰巻きの上に着る下着)がチラチラするのは、男性にはドキッとすることがあるのではないでしょうか。残念ながら江戸の女性は赤ではなく、無地の袖や裾からチラッと見えるのは水色なのだそうです。ただし、その道の女性は赤を使います。 |
||||
| 杉浦日向子の江戸塾 <続き> 26~ | ||||
| ↑ Page Top | ||||
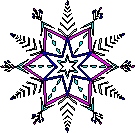 巳年→みどし→見通し へび年は「巳年」と呼ばれます。「巳年(みどし)」は「みとおし」すなわち「見通し」「見透し」に通じます。先見性をもって、判断し、行動することが求められています。グローバル化が一層進みますので、経営の意思決定の迅速さはさらに求められるでしょう。 |

